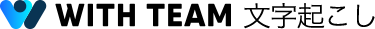会議の議事録は、単なる記録ではありません。情報共有や意思決定をスムーズに進めるための核となるものとして、多くの企業で分かりやすさが求められています。この記事では、よくある失敗を交えながら、誰でも使える分かりやすい議事録の書き方を詳しく解説します。
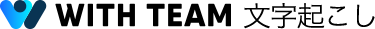
\議事録作成に時間がかかる「文字起こし」を最安値で代行します/
『WITH TEAM 文字起こし』では1時間以内の音源なら
中1日納期で1分120円~納品可能!
1000時間以上の大型案件も対応可能!
業界最安級の価格とスピード感を持って文字起こしの依頼が可能です。
まずはお気軽に無料お見積りからお試しください
目次
分かりやすい議事録が求められる理由
「頑張って作成したのに、なぜか要点が分からない…」
「ただの文字起こしになっていて、読みづらい…」
あなたも、そう感じた経験はありませんか?
まさに、こうした「分かりにくさ」を防ぐことこそが、質の高い議事録に求められる本質です。
分かりやすい議事録が求められる理由とは、会議の内容を正確に共有でき、かつ、後から確認した際に、誰もが即座に要点を把握できる必要があるからです。
特にリモートワークやプロジェクトの複雑化が進むなか、会議に不参加のメンバーが決定事項やその背景を把握できないと、業務に支障が出るリスクも否定できません。
分かりにくい議事録は、チームの生産性を著しく低下させます。
たとえば、重要な決定事項が曖昧で「結局、何が決まったの?」と業務が混乱する。あるいは、「誰が・何を・いつまでに」やるかが不明確なためにタスクが放置されたり、二重で作業してしまったりする。
さらには、「そんな話は聞いていない」といった「言った・言わない」のトラブルに発展し、同じ議論をやり直すために多くの時間と労力を浪費することにもなりかねません。
だからこそ、会議に参加した人もしていない人も、誰もが内容を正確に理解できる分かりやすい議事録が求められているのです。
議事録の作成でありがちな失敗とその原因
議事録の作成では、さまざまな失敗パターンがあります。ここでは、特に多い典型的なミスとその原因を見ていきましょう。
抜け漏れ・誤記・重要事項の記載忘れ
議事録作成で特に多い失敗が、重要な内容の抜け落ちや記載ミスです。どんなに詳細に書き取ったつもりでも、肝心の結論や担当が記載されていなければ意味がありません。会議で合意したはずの事項が記録から漏れていると、後日、「決まった内容が実行されていなかった」とトラブルになることがあります。
こうしたミスが生じるのは、「どの情報をどの順番で書くべきか」が担当者のなかで整理されていないことが原因です。会議中の議論をそのままメモするだけでは、肝心の決定事項や担当が、第三者が見たときにわかりにくい場合があります。それを防ぐには、議事録の項目や記録の流れを明確に定めておくことが必要です。
また、日付や人数、数量といった基本情報の誤記や記載漏れも多いです。たとえば、会議の開始時間や参加者名など、基本的な情報を間違えて記載してしまうと、後から訂正の連絡や記録の修正が必要になる場合があります。
これも、事前にチェックすべきポイントや記載ルールが共有されていないことが要因です。こうした小さなミスでも、余計な手間を増やすことにもなりかねないので注意しましょう。
決定内容や担当・役割が不明瞭
会議で何が決まったのか、誰が何を担当するのかが議事録から読み取れないという失敗も少なくありません。結論や必要なアクションが曖昧な状態で記録されていると、後から参加者に聞き直さなければならず、業務が停滞する原因になります。
発言録のように議論の経過だけが詳しく書かれ、肝心の結論や担当者、期限などが抜けているというパターンも多いです。そのせいで、関係者が「自分のタスクとは思わなかった」と認識してしまい、誰も動かないまま締切が過ぎてしまうこともあります。
担当や役割が不明瞭になる原因は、議事録の作成者が、決定事項やアクションプラン、担当割当を具体的に記載する必要があるという認識が不足しているからでしょう。「なぜそうなったか」や、誰が動くのかが分からなければ、議事録は機能しません。「誰が」「何を」「いつまでに」を明確に記録することが議事録の条件です。
作成に時間がかかりすぎる・情報がまとまらない
議事録の作成に時間がかかるという悩みもよく耳にします。会議が終わってもなかなか議事録をまとめきれず、結局、参加者に共有できたのが1週間後というケースも珍しくありません。
こうした遅れが生じる原因として考えられるのが、会議中に発言を一字一句書き留めようとするあまり、肝心の要点が整理できていないことでしょう。そのせいで、後から録音を何度も聞き返すことになり、議事録の作成に必要以上に時間がかかってしまうのです。
同様に、内容を詰め込みすぎて要点がぼやけてしまうという失敗もあります。議論の経緯や全員の発言をすべて盛り込もうとして、結論や重要事項が埋もれてしまっては本末転倒です。何を決めたのか分かりにくい議事録では、読み手は必要な情報をすぐに把握できず、そのせいで業務に遅延が生じることもあります。
以上、どちらの失敗も、突き詰めれば、「どの情報をどのようにまとめるべきか」という視点が不十分なまま議事録を作成しようとするために起こる失敗だと言えるでしょう。
【すぐに使える】議事録作成チェックポイントと基本フォーマット
わかりやすい議事録を作成するには、まず、どの項目をどんな順番で記録するかを決めておくことです。ここでは、どんな議事録でも共通して使えるポイントと基本的なフォーマットを紹介します。
✅議事録作成の基本項目のチェックポイント
- ・何の会議か、冒頭で分かるようになっているか
- ・議題やアジェンダがあるか
- ・各議題ごとの内容が簡潔にまとめられているか
- ・決定事項が明確に記されているか
- ・決定事項に対する今後のアクションがまとめられているか
- ・未決事項や保留事項が記されているか
- ・その他、次回の開催日時や場所、配布資料名などが記されているか
何の会議か冒頭で分かるようにしましょう
冒頭で何の会議なのかがひと目で分かるよう、会議名、日時、場所(オンラインの場合は拠点やURLなど)、出席者の氏名や所属を明記しましょう。
これらは一見当たり前に思えますが、後から議事録を検索したり、誰がその決定に関与したのかを振り返ったりする際に欠かせない情報です。役職や部署も記しておくと、責任の所在がより明確になります。
議題やアジェンダをまとめましょう
続いて、その会議で何を話し合ったのかを示す議題やアジェンダを列挙します。全体のテーマや流れを俯瞰できるように、たとえば「○○プロジェクト経過報告」「△△製品トラブル対応策検討」といった形で箇条書きにしておくとよいでしょう。
決定事項が明確に記しましょう
会議で決まったことは、議題ごとに決定事項としてまとめましょう。
「◯◯を実施する」「△△の方針で進める」など、何が決定されたのかを具体的に書き、見出しや太字で強調するのも有効です。決定事項が漏れなく記載されていれば、関係者が後から確認する際にも迷うことがありません。
決定事項に対する今後のアクションをまとめる
決定事項にもとづいて「誰が」「何を」「いつまでに」対応するのかを今後のアクションとしてまとめておきましょう。
主語、アクション内容、期限をセットで記載し、「〇〇が△月☓日までに●●を実施」のように具体的に書き残します。
未決事項や保留事項があれば記しましょう
議論したが結論が出なかったテーマや、次回に持ち越した課題などがあれば未決事項や保留事項として記録しておきましょう。明確に記録することで、次回以降の会議で抜け漏れを防ぐことができます。
次回開催日時や場所、配布資料名などがあれば記載しましょう
定例会議や継続するプロジェクト会議のように、次回の開催日時や場所が決まっていれば、併せて記載しましょう。
未定の場合でも「次回日程:未定」と明記しておけば、後から議事録を見返したときに混乱することがありません。
加えて、配布資料がある場合は、資料名や版数を記録しておくと、後日、資料と議事録を照合する際に役立ちます。
用途別・会議別の書き方の工夫
会議の種類や目的に応じて、議事録の書き方にも工夫が必要です。基本フォーマットは共通でも、定例会議なのかプロジェクトの意思決定会議なのか、あるいはトラブル対応会議なのかによって強調すべきポイントや項目の深掘り具合が変わります。
定例会議の場合
定例ミーティングでは、前回のToDoや進捗確認が中心となります。そのため、議事録には「前回からのアクション項目の実施状況」や「持ち越し課題」の欄を設けておくと、冒頭でやり残しやフォロー事項が整理しやすいです。また、毎回同じような議題が出る場合は、あらかじめ定番テーマをテンプレ化しておくことで、記録漏れや書き忘れを防げます。
プロジェクト会議の場合
プロジェクトのキックオフや意思決定会議では、「なぜその結論に至ったのか」「代替案がどう検討されたのか」など、議論の背景や選択肢ごとの比較が重要になります。意思決定の根拠を後から確認できるよう、選択肢のメリット・デメリットや経緯を具体的に記録しておくのがポイントです。
メンバーが多岐にわたる場合は、氏名・役職・部門などの基情報に加え、それぞれの役割や関与範囲を明確にしておくと、後から確認する際に経緯が分かりやすくなります。
トラブル対応会議の場合
クレームや障害対応の会議では、発生した問題の詳細や経緯、対応の流れを時系列で整理します。
タイムライン形式でいつ何が起きたのかを分かりやすく記載するとともに、原因分析や再発防止策も記録しておくと、後から振り返るときに役立ちます。顧客対応や社内説明にも使うケースが多いため、ポイントを箇条書きで分かりやすくまとめておくことが大切です。
分かりやすい議事録の書き方のコツ
分かりやすい議事録を作るには、単にテンプレートの項目を埋めるだけでは十分とは言えません。読み手が迷わず内容を把握できるよう、基本ルールに従いつつも、読みやすさを意識した工夫が必要です。ここでは、議事録の質を高めるためのポイントを解説します。
5W1Hと主語・アクション・期限の明確化
会議の内容を後から正確にたどれる議事録を作るには、「誰が」「何を」「いつまでに」をはっきり記載することが基本です。5W1H(Who・What・When・Where・Why・How)のうち、特に「Who」「What」「When」を意識して議事録を書きましょう。それだけで、情報の抜けや誤解を大きく減らすことができます。
たとえば、主語を省略した記述は読み手の誤解を招きやすいため、単に「~を実施する予定」とするのではなく、「〇〇部が△△を実施する予定」といった書き方を徹底します。
アクションの記述に関しては、「検討する」や「対応する」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇の資料を作成する」「△△へ確認の連絡を入れる」といった具体的な内容まで記載しておくと、実行段階でのミスや抜け落ちを防げます。
また、タスクの期限を具体的な日付や時間で示しておくことも大切です。たとえば「なるべく早く」ではなく「〇月〇日17時までに」と明記することで、優先順位や緊急度が伝わりやすくなり、会議後の動きが明確になります。
箇条書きや強調、図表の活用
議事録が長文ばかりだと、肝心な決定事項や要点が埋もれてしまいます。後から見返したときに必要な情報をすぐにつかめず、「結局、何が決まったのか分からない」といったことにもなってしまいがちです。そのため、視覚的な工夫として箇条書きや表を活用し、レイアウトを整理することを意識しましょう。
箇条書きは議事録を読みやすくする最も基本的な方法です。たとえば決定事項が複数ある場合は、「■決定事項」などの見出しの下に「・A案を採用する」「・来週中に資料を提出する」といった形で箇条書きにまとめます。文章内に埋もれさせるのでなく、要点を抜き出して並べると情報が一目で把握しやすいです。
また、賛成・反対など複数の意見があった場合にも、それぞれを箇条書きで整理し、発言者名や理由を添えると議論の経緯が分かりやすくなります。その際、「この意見」「その案」といった指示語に頼らず、具体的な内容を記載することが大切です。
重要な日付や決定事項などは、太字や下線で強調すると見落とし防止につながります。社内向けであれば色分けも有効ですが、印刷することを考慮して記号や囲みを使うなど、工夫するとよいでしょう。ただし、強調が多すぎると読みにくくなるため、本当に伝えたいポイントに絞って使うのがポイントです。
さらに、数字の比較や日程調整など、文章では伝わりにくい内容は、表や図を使って整理するとより分かりやすくなります。たとえば、プロジェクトの進捗状況を表で示したり、トラブル対応の原因と対策をマトリクスでまとめたりすると、関係者全員にとって状況を直感的に把握しやすくなるでしょう。なお、議事録の本文に組み込むのではなく、「詳細は添付資料を参照」とする形でも構いません。
最後に、文体や表記の統一も大切なポイントです。社内議事録は箇条書きを中心に簡潔にまとめることが多く、ですます調・である調いずれでも構いませんが、文末や用語の揺れは必ず揃えます。
過去の議事録やテンプレートを賢く活用する
議事録の品質を高めるには、過去の議事録や既存のテンプレートを積極的に活用することも必要です。毎回ゼロから書き起こすのではなく、既存の資産を生かすことで、抜け漏れや書き忘れを防ぐとともに、作業時間の短縮にもつながります。
定例会議の場合、前回の議事録を参照しながら進捗確認や持ち越し課題の整理を行えば、抜けがちなアクションアイテムも確実にフォローできます。また、議事録のレイアウトや項目立ても、前回のフォーマットをコピーして使えば、情報の比較がしやすく、読み手の負担軽減が可能です。
テンプレートを活用する場合、一度作ったものをそのまま使い続けるだけでなく、気付いた点は随時アップデートしましょう。
たとえば、「会議ごとに確認が必要な資料提出の有無」や「関係部署への連絡状況」など、当初は想定していなかった情報の記載が毎回必要になっていることに気付いた場合は、その項目を新たにテンプレートへ追加します。逆に、使われていない欄があれば思い切って削除します。
このように、実務に合わせて調整していくことが、より実用的なテンプレートを作るポイントです。担当者同士で「こんな工夫をしたら便利だった」というノウハウを共有し合うとよいでしょう。
蓄積した議事録は、ぜひ社内のナレッジとして活用してください。共有フォルダや社内Wikiなどで簡単に検索・参照できるようにしておけば、似たテーマの会議や新しいプロジェクトで参考にできますし、新人教育の教材としても役立ちます。
議事録の作成に役立つITツールとその注意点
近年、議事録作成の現場では自動文字起こしツールやAIアシスタントの導入が広がっています。音声をそのままテキスト化できるツールを使えば、手作業での書き起こしや転記にかかる手間を大きく減らすことが可能です。
ただし、効率化の効果は大きいものの、精度や実務との相性など、注意すべき点も存在します。ここでは、ITツールを賢く使いこなすためのポイントをお伝えします。
googleドライブで難しい文字起こしは専門サービスを検討しよう
googleドライブやgoogleドキュメントの音声入力やAI機能を活用すれば、会議やインタビューなどの文字起こしを簡単に行うことができます。
しかし、録音の音質が悪い場合や、話者が多い会議、専門用語が頻繁に登場する音声、長時間の動画ファイルなど、AIだけでは十分に対応できないケースも少なくありません。特に、内容の正確さが求められる医療や法律、学術分野の音源、複数の話者が入り乱れる座談会、音声が不明瞭な現場録音などでは、googleドライブの機能だけでは完璧な文字起こしは困難です。
このような場合、経験豊富な専門スタッフが音声内容を細かく聞き分け、専門用語や固有名詞の確認・修正まで丁寧に対応してくれる専門業者に依頼するのが賢明です。精度や納期、セキュリティなどの点でも、AIや自動化ツールにはない高品質なサービスを受けられます。重要な案件や作業負担を減らしたい場合には、ぜひ検討してみてください。
自動文字起こしツールやAIの特徴
自動文字起こしツールの多くは、会議の録音データをアップロードするだけで、数分後には全発言がテキスト化される仕組みです。会議中にメモを取りきれない場面でも、後から内容を確認できるため、進行役も参加者も議論に集中しやすくなります。
また、最近のAIツールは、発言者ごとにテキストを分割したり、キーワード検索やタグ付けができたりなど、議事録の下書きに役立つ機能を備えています。たとえば、発言の多かった参加者や重要なキーワードだけを抽出するといったことも可能です。
ただし、AIの精度がどれだけ向上しても、録音環境や発言の明瞭さに大きく左右されるのが現状です。複数人が同時に話したり、小声や早口で発言したりすると、どうしても誤変換や抜け落ちが起こりやすくなります。また、固有名詞や業界独特の専門用語、略語なども誤記録されやすいポイントです。そのため、会議の冒頭で録音を開始することを宣言し、参加者にできるだけクリアな発言を心がけてもらいましょう。
AIでできること・できないことを踏まえた活用法
AIで自動化できる作業が増えたとはいえ、ツール任せにするだけでは議事録の品質は保てません。
AIが出力したテキストをそのまま配布するのではなく、担当者が必ず一度目を通し、誤変換や抜け漏れ、文脈のずれがないかをチェックする必要があります。特に、決定事項やアクションアイテムなど、業務上影響の大きい部分は人の目による確認が欠かせません。
AIツールを最大限に活用するには、「どこまでをAI任せにし、どこからを人が手直しするか」の切り分けをあらかじめ決めておくことです。
たとえば、「議論の流れや発言の全体像はAIでカバーし、最終的な結論やタスクは人が整理して記載する」など、役割分担を明確にすれば、無駄な作業やチェック漏れを防ぐことができます。また、会議の内容や重要度によって、「この部分だけは手作業でまとめる」「専門用語は自分で補記する」といった工夫も大切です。
AIが作成したものはあくまでたたき台です。議事録を作成する際は、そのたたき台を活用しつつ、誤変換や意図のブレを修正し、読み手に伝わりやすい内容に仕上げることを常に意識してください。
議事録を確実に残すなら専門業者に依頼しよう
分かりやすい議事録を残すには、単に会議内容を記録するだけでなく、誰が読んでも経緯や決定事項が正確に伝わるよう意識して整理することが大切です。基本のフォーマットや書き方を押さえたうえで、5W1Hの明確化や箇条書き、図表、過去資産の活用など、わかりやすくなるように工夫してみてください。
また、便利な自動文字起こしツールやAIですが、最終チェックは必ず人の目で行うことも忘れないようにしましょう。
もし、毎回の議事録作成が負担になっているなどの課題を感じている場合は、専門業者に依頼することも賢明な選択です。必要に応じて外部サービスも賢く取り入れ、自社に最適な形で議事録作成の体制を整えてください。
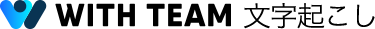
\対応オプション多数!文字起こしは『WITH TEAM』がおすすめです/
『WITH TEAM 文字起こし』では1時間以内の音源なら
中1日納期で1分120円~納品可能!
1000時間以上の大型案件も対応可能!
業界最安級の価格とスピード感を持って文字起こしの依頼が可能です。
まずはお気軽に無料お見積りからお試しください