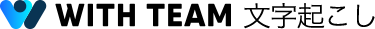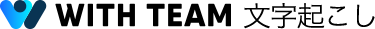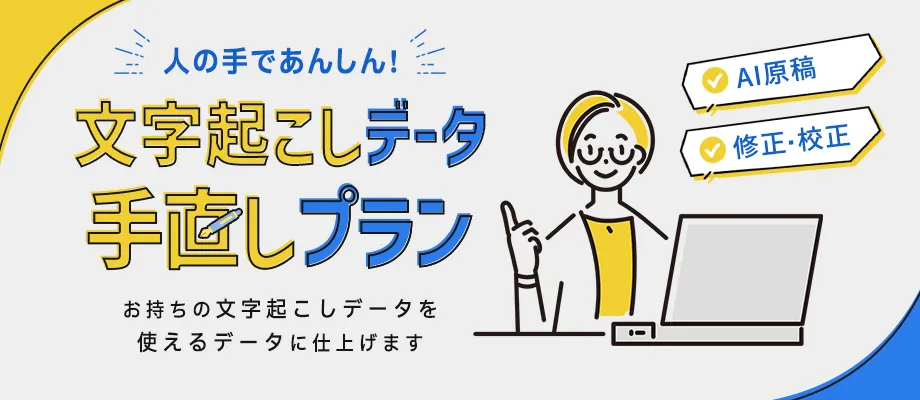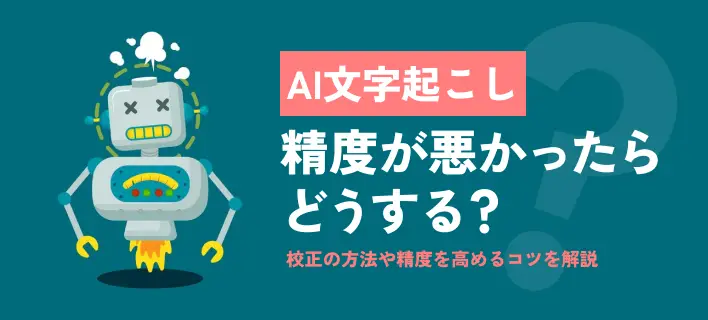
近年、AIによる文字起こしサービスは、会議やインタビューの記録、動画の字幕作成など、様々なシーンで活用されるようになりました。
しかし、実際に利用してみると「期待したほどの精度が出ない」と思うことがありませんか。特に企業のコンテンツ制作においては、誤字・脱字は、ブランドイメージや顧客からの信頼低下、さらには法的な問題に発展するリスクさえ孕んでいます。それだけに、正確な文字起こしがとても重要です。
本記事では、
- ❶AI文字起こし原稿の精度が低かった場合の対処法
- ❷AIで作成した文章を修正するコツについて
- ❸文字起こし校正サービスについて
など実践的な視点から詳しく解説します。
目次
AI文字起こしの進化と限界
AI文字起こし(テープ起こし)は、ディープラーニングなどの技術の発展により、近年目覚ましい進化を遂げています。しかし、まだ人間には及ばない部分もあります。
簡単に言えば、AIは大量の音声データと、それに対応するテキストデータを学習することで、音声を文字に変換する技術を学習します。例えるなら、たくさんの絵を見て、それが「犬」なのか「猫」なのかを学習するようなものです。
しかし、一般的なAI文字起こしは、「音」を「文字」に変換する精度は向上していますが、同音異義語の使い分けや、話者の意図を汲み取った自然な表現への変換といった、高度な意味理解を必要とする処理はまだ苦手としています。
つまり、これが、現地点でのAI文字起こしの限界と言えるでしょう。この限界を理解することが、この後に説明するAI文字起こし後の校正や編集が重要な理由につながります。
AI文字起こし後の校正・編集の重要性
AI技術は日々進化しているものの、人間の耳や脳のような高度な情報処理能力にはまだ及んでいません。AIは音声を認識し、単語や文章に変換することはできますが、文脈やニュアンス、話者の意図などを完全に理解することは難しい場合があります。
そのため、AI文字起こし(テープ起こし)を利用後は、校正・編集作業が非常に重要となります。
例えば、以下のようなケースで誤変換が発生する可能性があります。
- 同音異義語: 「きょう」という発音は、「今日」「経」「強」などに変換される可能性がある。
- 専門用語: 特定の業界や分野で使われる専門用語は、AIが正しく認識できない場合があります。
- 音声の品質: ノイズが多い環境で録音された音声や、話者の発音が不明瞭な音声は、AIの認識精度が低下する原因となります。
- ケバ(言い淀み、言い直し): 「えー」「あのー」といった言い淀みがそのままテキスト化されてしまい、文章が読みにくくなることがあります。
これらの問題を解消し、より正確で読みやすいテキストを作成するためには、人間の目による校正・編集が不可欠です。
AI文字起こし後の校正・編集でチェックすべき5つのポイント
では校正・編集では何をチェックすればよいのか、どんなことに注意すべきなのでしょう。ここでは、AI文字起こし(テープ起こし)後の校正・編集でチェックすべき5つのポイントを紹介します。
漢字の誤変換・誤用
AI文字起こしの精度は向上していますが、文脈の把握が難しい場合や、突然話題が変わる場面では漢字の誤変換が発生しやすくなります。特に、専門用語や固有名詞は誤認識されやすく、人名、地名、専門用語などで誤りがないか重点的に確認する必要があります。
例:「見る」と「観る」
誤変換された文: 「映画を見る。」
正しい文: 「映画を観る。」
発話の重なり部分
複数人が同時に話している音源は、AIが正確にテキスト化することが難しく、文章の区切りが不適切になったり、複数の発言が混ざったテキストになったりする場合があります。
例:
・Aさんの発言中にBさんの相槌(「はい」「ええ」など)が挿入され、Aさんの発言の一部として認識されている
・複数の発言が途中で混ざり合い、意味不明な文章になっている
このような場合は、発言者ごとに文章が正しく区切られているか、発言の中に他の人の発言が混入していないか、文末が適切に処理されているかなどを注意深く確認する必要があります。
語彙の認識と修正
AIは丁寧で正確な言葉遣いを認識する精度が高い一方、日常会話でよく使われる砕けた表現や省略語、言い間違いなどは正しく認識できない場合があります。文字起こし自体は発言通りに行われていても、文章として読みやすくするために修正が必要な箇所が出てきます。
例:
・「〜じゃないですか」が「〜ではありませんか」と変換されている
文脈によっては修正しない方が自然な場合もある
・「〜とか」のようなあいまいな表現がそのまま残っている
このような箇所は、文脈に合わせて適切な表現に修正する必要があります。
句読点の修正
句読点は文章の意味や読みやすさに大きく影響します。AI文字起こしでは、息継ぎなどのわずかな間を句読点として認識する傾向がありますが、必ずしも適切な位置に句読点が打たれているとは限りません。
例:
・読点が多すぎて文章が途切れ途切れになっている
・必要な箇所に句読点がなく、文章が長くなっている
修飾語と被修飾語の関係や、主語と述語の関係などを考慮し、文脈に合った適切な位置に句読点を修正することで、文章の可読性を高めることができます。特に読点の位置は意味を変えてしまう可能性があるので注意が必要です。
文法の修正
Web記事など、一般読者向けの原稿を作成する場合は、話し言葉の文法的な誤りを修正し、読みやすい文章にすることが重要です。AIは文法ミスをそのままテキスト化するため、人間の手による修正が必要となります。
例:
・主語と述語が一致していない
・助詞の使い方が不適切
ただし、裁判の証拠など、発言内容を忠実に記録する必要がある場合は、文法的な修正を行うことで証拠としての価値を損なう可能性があるため、注意が必要です。どこまで修正を行うかは、ケースバイケースで判断する必要があります。
これらの5つのポイントを踏まえることで、AI文字起こしの精度を高め、より正確で読みやすいテキストを作成することができます。
それでもAI文字起こしの精度が悪い時はどうすればいい?
「AI文字起こしツールは便利だけど、誤字や不自然な言い回しが多くて、結局自分で修正するのに時間がかかってしまう…」
「AIの原稿はあるからこれを使って修正してくれないかな?」
弊社の文字起こし代行サービスでも、お客様からこのような声を頂いております。
そこでおすすめしたいのが、人の手でAIの文字起こし原稿を丁寧に修正・校正してくれる「文字起こしデータ手直しプラン」です。
文字起こしデータ手直しプランとは?
AI文字起こし(テープ起こし)校正サービスとは、AI文字起こし原稿の校正・作業を専門のライターが代行するサービスです。
AIツール等で起こした現行の間違い(誤字・聞き間違い・読みづらい)をプロの手によって手直しを行い納品いたします。自分で文字起こしをした原稿にもしっかり対応します。
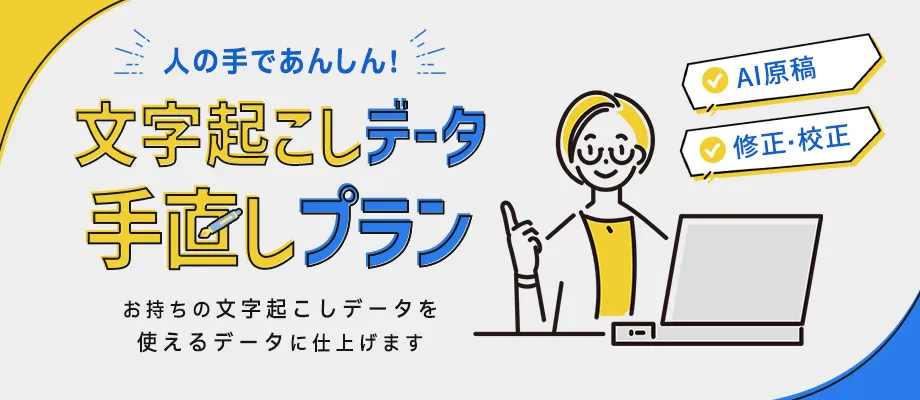
■どんな手直しをしてくれる?
- ・誤字脱字や誤変換の修正
- ・不自然な句読点の調整
- ・AIが聞き取れなかった部分の補完
■原稿の実際の仕上がりはどんなもの?
- ・けばとりを選択した場合:「えー」「あのー」といった不要な言葉の除去
- ・簡易整文を選択した場合:話し言葉を自然な書き言葉にリライト
AIのスピードと、プロによる正確性を掛け合わせることで、文字起こしの品質を格段に向上させることができます。AIの生成結果に満足していない方、修正作業の時間を他のコア業務にあてたい方は、一度プロの手によるリワークを検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
AI文字起こしは、コンテンツ制作のプロセスを劇的に効率化する強力なツールです。しかし、AIには文脈の理解やニュアンスの汲み取りに限界があるため、その結果を「下書き」と捉え、人の手による最終確認と修正を加えることが、信頼性の高いコンテンツを仕上げる鍵となります。
本記事で解説した、
- (1)漢字の誤変換
- (2)発話の重なり
- (3)語彙の認識
- (4)句読点
- (5)文法
といった5つのチェックポイントを意識するだけでも、AIが生成したテキストの品質は格段に向上します。
もし、ご自身での修正作業に時間がかかりすぎる場合や、より専門的な精度が求められる場合には、プロの校正サービスに依頼するのも有効な選択肢です。
AIのスピードと人間の正確性・判断力を組み合わせる「協業」の視点を持ち、AI文字起こしを賢く活用していきましょう。